食堂の正社員を辞めたあと、
次の転職先が決まるまでの1年3ヶ月間、
私は単発の派遣の仕事を転々としながら、なんとか生活費をつないでいました。
当時の私には、まだ「これを一生の仕事にしたい」と言えるものはなく、
とりあえず目の前の生活を回すことで精一杯でした。
そんな中で出会ったのが、
あとになって大きく人生を動かすことになる「灯油販売の冬季バイト」です。
ここからは、そのときに経験した灯油販売の裏側と、
そこで芽生えた気持ちの変化について振り返っていきます。
灯油の冬季バイトを始めたきっかけ
そんなときに見つけたのが、
灯油の巡回販売の期間限定アルバイトでした。
勤務期間は9月〜翌年3月まで。
掛け持ちしていた頃の仕事よりも給料がよく、固定給に加えてインセンティブつき。
しかもノルマなしで、「頑張った分だけ稼げる」という好条件でした。
成績次第では社員登用の可能性もあるとのことで、
当時の私にはとても魅力的に見えました。
灯油販売の仕事の裏側
仕事内容は、3トンのタンクローリーに一人で乗って、
いくつかの担当地域を巡回しながら給油していくというものです。
18リットルのポリタンクはもちろん、家庭用ボイラーや、
工場で使うドラム缶への給油も担当していました。
本格的に寒くなるまでは、まず巡回地域でチラシを配って、
「毎週水曜日の15時ごろに、このエリアを灯油販売で巡回します」
といった案内をしながら、
少しずつ存在を知ってもらうところから始まります。
私は6つのコースを担当していて、
1日に回るのはそのうち1コースだけ。
1コースあたり、約8箇所の地域を巡回する形でした。
季節が進んで少しずつ寒くなってくると、
巡回先の家の玄関先に、目印のようにポリタンクが置いてあったり、
通りかかったときに「灯油お願いしまーす!」と呼び止められたりします。
足腰が弱い高齢の方や、団地の高層階に住んでいる方も多く、
こちらが給油に行くと、本当に嬉しそうに感謝の言葉をかけてくれました。
その一言一言が、当時の私には大きな支えになっていました。
冬になると、住宅街や団地のあたりで、
音楽を流しながらゆっくり走っている灯油のタンクローリーを
見かけたことがある方も多いと思います。
実はあのときに流れている音楽は、灯油販売業者ごとに違うんです。
「このメロディはあの会社だな」と聞き分けられる人もいるかもしれませんね。
深夜まで走り続けた日々と「ありがとう」の重み
やりがいは十分にあったものの、冬本番になると状況は一変します。
とにかく需要が多すぎて、タンクローリーの灯油(2000リットル)が
あっという間に空になってしまうのです。
給油所に戻って補充しては、また巡回に出る。
その繰り返しで、とても予定していた時間通りには回りきれません。
それでも、タンクを玄関先に出して待ってくれている人たちのことを思うと、
「もう少しだけ」と夜遅くまで走り続けていました。
日付が変わる頃まで巡回していた日もあります。
体はクタクタでしたが、「ありがとう、助かったよ」と
直接言ってもらえることが多く、仕事そのものはきついだけでなく、
むしろ喜びすら感じていました。
それまで私は、「商品を売り買いしてお客さんから感謝される」
という経験をしたことがありませんでした。
仕事なんて、感謝されないのが当たり前だと、どこかで思っていたんです。
でも、この灯油販売の仕事を通して、
「助かったよ、ありがとう」と直接言ってもらえる場面が何度もありました。
そのたびに、自分の仕事が誰かの役に立っている実感があって、
少しずつ自分に対する見方も変わっていった気がします。
トラック運転との出会いと新しい興味
もうひとつ、大きな変化がありました。
普通車以外の“運搬用トラック”に乗れるという発見と、
「自分でもこういう車を運転できるんだ」という自信が持てたことです。
そして何より、
「運送の世界って、意外とおもしろいかもしれない」
そんな興味が、自分の中に芽生え始めていました。
そして、満期を迎えた3月。
正社員登用の話こそありませんでしたが、
毎日働き詰めだったおかげで、お金を使う暇もほとんどありませんでした。
その結果、当面の生活には困らないくらいの貯金ができていました。
その貯金があったせいで、どこか「まあ、そのうちなんとかなるだろう」と、
少し楽観的になっていたところもあったと思います。
引き続き転職活動を続けていた私は、
「トラック運転」という新しい選択肢が加わり、
運送業の求人ばかりを眺める毎日を送っていました。
一本の電話
そんなある日、灯油販売のアルバイト時代に
同じタイミングで入ってきた同年代の同僚から、久しぶりに連絡がきました。
「元気してる? 飯でも行かない?」
特別仲が良かったわけでもないのに、
なぜかその誘いに乗ってしまった私。
正直、「奢ってもらえるならラッキー」くらいの軽い気持ちで、
深く考えずにOKしてしまいました。
今思えば、この“なんとなく”が、一番危なかったのかもしれません。
彼は大きなアメ車で迎えに来ました。
「美味しいラーメン屋があるから、そこに行こう」と言います。
車内では終始、特に話が弾むわけでもなく、
彼もどこか歯切れの悪い様子で話していました。
連れて行かれたラーメン屋の味は、
正直お世辞にも美味しいとは言えませんでした。
ぬるいスープだったことだけは、今でもよく覚えています。
お会計は彼が出してくれました。
しかし、帰りの車の中で、彼は唐突にこう切り出してきたのです。
「……ちょっとさ、お金貸してくれへん?」
▶次回予告
お金を貸した相手は音信不通・着信拒否となり、電気もガスも止まった極貧生活のなかで、私は完全に追い詰められていきます。

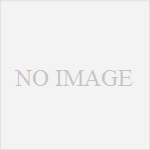
コメント